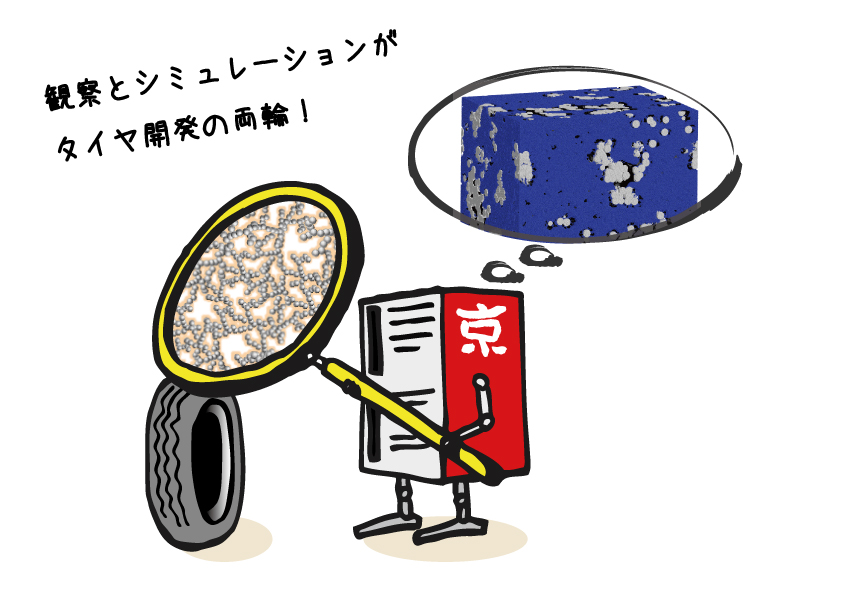東京モーターショー2015で「京」を使った新材料開発技術が生み出した新しいタイヤが公開
安全!快適!地球にやさしい!自動車のコマーシャルにはこんな言葉がよく使われています。これらの性能に深く関わる自動車の部品がタイヤです。2015年10月の東京モーターショーで発表された、住友ゴム工業株式会社(以下、住友ゴム)の新しい材料開発技術には「京」が活躍しています。
「安全性能」「低燃費性能」「耐摩耗性能」すべてを兼ね備えるのはむずかしい
タイヤが備えるべき性能は数多くありますが、今後のタイヤ開発において特に重要となる性能が3つあります。
1つめは、安全性に係わるゴムのグリップ性能です。特に、雨の日でもしっかり止まる性能が重要です。
2つめが、低燃費性能、つまりタイヤが転がる時のゴムの発熱を抑え、転がり抵抗を低減し、自動車の燃費を向上させる性能です。
そして、3つめが、耐摩耗性能などに関わるゴム強度です。
これら3つの性能をどのようにして同時に向上させるかということになりますが、難しい点はそれぞれが相反する性能であるということです。例えば、低燃費なタイヤにするためには地面との摩擦を小さくし、よく転がるようにする必要があります。金属製の電車の車輪がまさにそれです。しかし、自動車は線路ではなく道路を走るので、摩擦が少ない固いタイヤは地面の上を滑ってしまい、ブレーキが効きません。曲がることも難しくなります。またタイヤが固ければ、道路のデコボコがそのままお尻に伝わって乗り心地も悪くなりそうですね。このように相反する性能をどのように実現するかが、タイヤメーカーにとって大きな課題です。
タイヤの材料に着目!
各タイヤメーカーによる相反する性能の向上に向けた取り組みの一つが、新しいゴム材料の開発です。ゴム材料を詳しく見ると、高分子ポリマー、ポリマーを繋ぐための架橋剤(硫黄)や結合剤、ゴムの補強材であるフィラー(カーボンブラックやシリカなどのナノ粒子)などが複雑に積み重なっています。ゴム材料の内部構造がどうなっているのか分子レベルから理解し、コントロールし、新しい材料を開発することが、求められているタイヤを作るために不可欠なのです。
「京」も活躍!ナノレベルのシミュレーションを使った新しい材料開発技術
住友ゴムが発表した新材料開発技術「ADVANCED 4D NANO DESIGN」を使えば、ナノ(1ミリの100万分の1)からミクロ(1ミリの1000分の1)のレベルでゴム材料を解析・シミュレーションすることが可能です。住友ゴムは、大型放射光施設「SPring-8」や、大強度陽子加速器施設「J-PARC」でゴムの内部構造や分子の運動を高い精度で観察、これまでにない高精度なデータを得ることに成功しました。これらのデータに基づいて、詳細で、しかも広い領域におけるゴム材料の分子構造を「京」に再現、シミュレーションを行うことで、ゴム内部でどのように破壊や発熱が起こるのかを明らかにしたのです。こうした解析に基づいてタイヤにかかるストレスの原因を特定し、減らすことで、「安全・快適・エコ」性能を向上させることが可能になりました。将来の製品化へ向けて
今回のモーターショーではこの技術を使って、低燃費性能やグリップ性能(カーブを曲がる・ブレーキの効きなどに関わる性能)を維持しつつ、擦り減りにくい高耐久性をもつタイヤが公開されました。「京」を使ったシミュレーションによって生み出された高性能なタイヤがお店に並ぶ日は、近いうちにやってくるかもしれません!
プレスリリース
説明動画